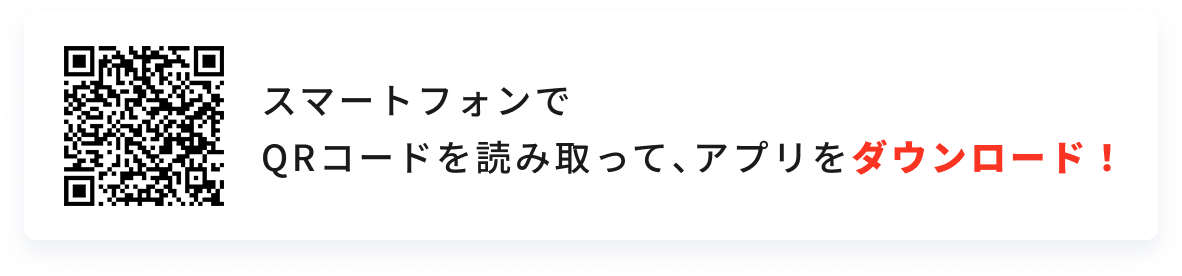田舎留学プロジェクト事務局でボランティア班・広報班リーダーを務めております、早稲田大学人間科学部 3年の河本結生です。はじめに、3月から続けてきたクラウドファンディングについて。今回の目標金額は698,800円。未達成の場合は全額が返金されるAll-or-Nothing方式という、まさに背水の陣とも言える状況の中、皆さまには長きにわたりご支援・ご協力をお願いしてまいりました。その結果、多くの方々から温かいご支援や情報拡散など力強い後押しをいただき、先日、無事に目標金額を達成することができました。本当にありがとうございます。5月10日に南伊豆町を訪れた際にも、町内各所に田舎留学プロジェクトのパンフレットやクラウドファンディングのチラシを掲示していただいている様子を目にし、改めて町の皆さまのご協力あってこその活動であることを実感いたしました。また、もともと南伊豆とご縁のなかった方々からも応援の声をいただく機会が増えています。本プロジェクトが少しずつ広がりを見せていることを大変嬉しく思うと同時に、改めて皆様に深く御礼申し上げます。ここで少し、田舎留学プロジェクト事務局の紹介をさせていただければと思います。田舎留学プロジェクト事務局は、事務局長を務める三井、人事班リーダーを務める山下、宿班・プロジェクト班リーダーを務める中村、そしてボランティア班と広報班のリーダーを務める私河本の計4名で構成されています。大学のワークショップで知り合った2023年12月から今日に至るまで、4人で全力で活動してまいりました。私がリーダーを務めるボランティア班と広報班についてもご説明を。ボランティア班では、9月に実施を予定している「つながる田舎留学」に向けて、参加学生がお手伝いをさせていただく町内事業者の皆さまとの調整を進めています。町のみなさんとの密な関わりを重視している本活動において、町と参加学生とを繋ぐ役割を担っています。広報班では、さまざまな広報媒体を通じて、情報発信を行っています。具体的には、南伊豆町回覧板(毎月1日・15日)や広報みなみいず(隔月)をはじめ、SNS(Instagram・X・Facebook・note・公式ホームページ)でも定期的に発信しています。ぜひご覧いただけますと幸いです。最近では、こうした媒体を通じて私たちの活動を知ってくださる方も増えているようで、町内外を問わず認知度が高まっていることを大変嬉しく感じています。大学では、4月より環境デザイン学ゼミに所属しています。建築や都市を対象としたフィールドサーベイを通じて、人間と環境の相互関係を明らかにすることを目指し、佐藤将之教授のもとで学んでいます。4月には、ゼミ活動の一環として兵庫県上郡町を訪問しました。同町は、佐藤教授が梅田修作町長の指導教員であったご縁から、早稲田大学人間科学学術院とまちづくり・教育分野で連携協定を締結しています。今回は町内各所への本棚設置に向けた現地調査を実施しました。町の中に本棚を設置することで、本を介して人と人とがつながる機会を生み出し、地域内での交流の促進を図ることが目的です。今後は今回のフィールドワークをもとに、設置場所や本棚のデザイン、交流を生みやすくする仕掛けなどを検討し、夏頃の設置を目指して準備を進めていきます。田舎留学プロジェクト、そして上郡町での活動のいずれにも共通しているのは、人と人とのつながりを大切にしている点。私自身、ボランティアや地域活動の経験は決して多くはありませんでしたが、南伊豆への思いを原動力に、活動をしてまいりました。これまで田舎留学プロジェクトを共に形にしてきた事務局メンバー、そして近々加わってくれるであろう新たな仲間たちとともに、今後もより一層、人と人、そして地域と人をつなぐ活動に励んでまいります。最後になりますが、これからの私たちの活動においても、変わらぬご支援、ご声援をいただけますと幸いです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。