【 目標額到達の御礼とネクストゴール 】クラウドファンディングは目標額到達後も最終日まで続きます
おかげさまで、5月9日(金)に目標額である¥698,800に到達しました。ここまでご支援いただきました皆様、SNSなどでの拡散やまわりへのお声がけにご協力いただきました皆様、チラシの配架や掲示にご協力いただきました町内事業者の皆様、本当にありがとうございます。施策は経済的に実行可能となりましたが、本番である「つながる田舎留学」をはじめとしたイベントはまだまだこれからです。東京での新歓活動やボランティア先となる事業者様との調整など、順調に進んでおります。
クラウドファンディングはネクストゴールを設定しまして、最終日まで継続して行われます。最近ではリターンも増え、町民の皆様だけでなく、南伊豆へ来たことがない皆様もご支援いただきやすくなりました。最終最後まで、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
お知らせしておりました通り、目標額を超えた分につきましても、プロジェクトの運営にかかる費用に充てさせていただきます。ご支援いただきました金額をもとに、運営局内各班に配分し、各班の主体性と責任のもとで大切に使わせていただきます。なお、上述の使徒に加え、お選びいただきましたリターンの仕入れ費用が発生します。リターンにより仕入れの費用は異なりますので、現状は上述に加えておりません。
一例ですが、以下のようなことに使用させて頂く予定です。
◯「つながる田舎留学」参加者が負担する宿泊費や食費の補填
参加者にかかる費用は現状、最大¥50,000を見込んでいます。主たる私たちの活動拠点である早稲田大学では、地方から上京して一人暮らしの学生も多く、経済的にはあまり費用を支払うことができません。個人にかかる経済的な負担を軽減することにより、より多くのひとが関心を持ってくれるものと考えます。
◯ 班ごとのFWの増強
運営局全体のFWに加え、ボランティア班、プロジェクト班など班ごとのFWを重ねることが「つながる田舎留学」の効果を高めることにつながると考えています。少人数の訪問が可能になることで、ニーズに応じて様々な日程や規模感でFWを行い、より密接な関係構築につながることが期待されます。
◯ 関係人口創出に寄与する追加企画の検討/実施
今後、田舎留学プロジェクト運営局のメンバーを新たに迎え、彼らの志や経験、南伊豆でチャレンジしてみたいことなどを実装する費用を補填します。「つながる田舎留学」に限ること無く、さまざまなかたちで学生が継続的に町に関わるきっかけを提供します。このことにより、南伊豆町を訪れる人々の幅や総数が向上することが期待されます。
◯ 広報活動の強化
広報活動にあたり、チラシやビラを印刷して町内や早稲田大学近辺に掲示、配架しております。今後も継続して情報発信を行い、クラウドファンディング等のご支援のお願いにとどまらず、このプロジェクトや町そのものの魅力発信にも寄与します。
【 自己紹介 】南伊豆町が大好きで、町の未来のために活動するグループです
南伊豆町を都会の若者にとっての「第二の故郷」とするための一大プロジェクトが始まります___。今までにないさまざまな交流を通して、学生と南伊豆町のみなさんとの間で相互的な関係を構築し、南伊豆町と関わる若い「関係人口」を増やすことによって、未来の町の担い手を確保することを目指します。

はじめまして。私たちの実施しているクラウドファンディングにご興味を持っていただき、ありがとうございます。私たちは「2023年度早稲田大学地域連携ワークショップ(南伊豆町)」から派生し、設立された任意団体「田舎留学プロジェクト 運営局」です。現在は南伊豆町長より委嘱を受け、南伊豆町長特命プロジェクト「田舎留学プロジェクト」事業推進スタッフとして無償のボランティア活動を行っています。
24年10月の委嘱を受け、施策の実施のために早稲田大学を拠点とした主体的な活動のために「田舎留学プロジェクト 運営局」を設立しました。私たちは町役場、早稲田大学、町民の皆様など多くの方々のご協力を得ながら、25年9月に実施を予定している「つながる田舎留学」を主軸とした南伊豆町の関係人口増加のために活動している有志の早大生の集まりです。
【 これまでの経緯 】あたたかい南伊豆町民のみなさんに惹かれて
私たちは「2023年度早稲田大学地域連携ワークショップ(南伊豆町)」にたまたま参加した、学部も学年も興味関心も出身もバラバラの4人組です。
本ワークショップは、まちづくり、地域ブランド、移住定住、お⼟産、観光・・・・⾃治体が抱える課題の解決策を、学⽣チームが提案する実践型ワークショップです。学部・学年を超えて集まった学⽣同⼠が議論しながら仮説を⽴て、⾃治体関係者や住⺠の⽅々へのヒアリングなどを通して提案につなげます。地域の魅⼒を知り、課題を深く考え、仲間と協働することは、成⻑の機会になります。(早稲田大学グローバルシチズンシップセンター https://www.waseda.jp/inst/sr/assets/uploads/2023/11/guideline_minamiizu_2023.pdf より引用)
私たちは、南伊豆町役場より「観光客から”関係⼈⼝”へ 若者が南伊⾖に関わる施策を考えよう」というテーマを与えられ、町民や町内事業者のみなさんに対し、オンラインヒアリングや対面でのインタビュー、実地調査などを行い、町の特性の理解、問題の本質の特定、課題の根本的な解決のための施策の提案を行いました。ワークショップは約2ヶ月でしたが、ほぼ毎日ミーティングを行い、毎日南伊豆町と向き合いました。あるメンバーは町長に対し「ワークショップ期間中、私たちが東京で一番南伊豆町のことを考えていた自信がある」と豪語したほど。それはきっと間違いではない、と思うほど、頭の中は南伊豆町でいっぱい。この期間を通して、単にワークショップで学びたいということだけでなく、伊勢えびや金目鯛をはじめとした美味しいご飯、ユネスコジオパークにも登録されている豊かな自然、なにより行く度にあたたかく迎えていただく町のみなさんの虜になっていました。私たちは南伊豆町を「第二の故郷」のように想い、ワークショップ後も継続して町に関わり、自らも関係人口として貢献したいという想いが強くなりました。
ワークショップにて頭がねじれるほど検討し、考案した施策である「田舎留学プロジェクト」を南伊豆町役場湯けむりホールにて、町長をはじめとした役場のみなさん、商工会さん、観光協会さん、地域おこし協力隊の方々などに向けてご提案させていただきました。通常、ワークショップはここで終了になるものの、その後役場には「早大生にご提案いただいた施策、ぜひやってほしい」といったご要望やご意見が多数。町長にも熱い応援をいただき、晴れて「南伊豆町長特命プロジェクト」として事業化が決定したのです。

【 プロジェクトの意図 】関係人口こそ町の未来


日本全体の人口減少や高齢化に伴って、南伊豆町は将来的な担い手不足の問題を抱えている、日本に数多い典型的な過疎地域です。多くの地方自治体では移住促進策に力をいれているものの、そもそもの人口が少なくなっていく中では「パイの取り合い」になり得ます。特に、伊豆半島には魅力的な周辺自治体が多く、依然として南伊豆町はその独自性を見出すことは必須ではあるものの、独自性を見出してもなお、急激な移住者の増加は見込めません。そこで国は第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のなかで貴重な若い労働力を複数市町村で共有する、いわゆる「関係人口」を地域の力とすることを目指すこととしました。ひとりのひとが複数の町の担い手として活躍することができれば、日本の地方にふたたび活気が戻ることでしょう。南伊豆町も関係人口増加のため、企画課地方創生室を中心に取り組んでいるところです。
*総務省 関係人口ポータルサイトhttps://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/
2023年度地域連携ワークショップにおいて、南伊豆町役場から提示されたテーマは「観光客から関係人口へ 若者が南伊豆と関わる施策を考えよう」です。本テーマ内にある「関係人口」になるということについて、私たちは「住まずとも町の一員」になるということと捉えました。それはつまり「南伊豆町への観光を友達に勧める」「ふるさと納税で返礼品として南伊豆町の美味しい干物が欲しい」「南伊豆町を将来の移住の選択肢にしたい」「なんとなく南伊豆町のニュースや出来事が気になってしまう」といった、南伊豆町を自分ごととして捉える人々のことです。
例えば、単なる観光とは、一般に南伊豆町のみなさんが訪問者に対して観光サービスや宿泊先、食事などを提供し、訪問者が単にそれを受容することです。しかし、それは一方的な関係性かつ多くが1、2日程度の極めて短期間の滞在であるため、南伊豆町のコミュニティには深く接触していません。私たちが南伊豆町の魅力であると感じた外部者に対しての高い受容性からくる人のあたたかさを感じる前に帰ってしまい、南伊豆町を自分事として考えることはないでしょう。そのため、南伊豆町を訪れる観光客はどれだけ多くても「町の一員」にはあたらず、関係人口増加にはつながらないのが現状であり、依然として町の未来の担い手不足が問題視されています。
「つながる田舎留学」においては、お手伝いや学校における授業、さまざまなイベントへの参加といった交流を通して、参加学生と南伊豆町のみなさんの間で相互的な関係を構築し、従来の観光体験の枠を超えた「町の一員になる疑似体験」が実現します。ご近所関係が希薄な都会に住む私たち学生にとって、南伊豆町のみなさんと深く関わる体験は、本留学期間外や大学卒業後にも継続して南伊豆町と関わるきっかけになります。「南伊豆のおじいちゃんおばあちゃんに会いに行きたい」「またみんなで団らんしながら美味しい南伊豆のご飯を食べたい」「南伊豆でなら今考えているあんなビジネス、こんなボランティアできるかも」と、田舎留学後の次のステップへの想像が広がります。このようなサイクルを通し、将来的に関係人口の増加に顕著な効果をもたらします。
町役場だけでは関係人口になる町外の人々にもリーチしにくいなど、様々な問題があり、なかなか上手くいっていない現状があります。田舎留学プロジェクトは町役場のリソースだけでなく、民間企業や大学機関などさまざまなアクターのご知見の共有や金銭的ご支援、学生の情熱と学術的知見など、いままで関係人口の増加のためには利用されてこなかったようなリソースを利用することによる、今までにない絶大な関係人口創出効果を期待しています。つまり、このプロジェクトは日本の現状、国の指針、町の想い、そして私たちの情熱があわさってできた、町の未来をつくる一大プロジェクトなのです。
田舎留学プロジェクトは南伊豆町と東京の大学生の橋渡しとして、関係性を構築する機会を与え、「また帰ってきたい」「もっと町に貢献したい」という若者を生むポテンシャルがあります。将来的な移住、都市部との二拠点生活、町内でのビジネスなど、学生ひとりひとりの個性や学びを南伊豆町と結びつけていくことができるでしょう。そのためには、私たちや役場のみなさんだけでなく、多くの方々のあたたかいご支援が必要です。
【 プロジェクトの具体的内容 】伊豆の最南端で第二の故郷をつくる
今年の夏に「つながる田舎留学」と題した30名の学生による町内での滞在イベントを企画しています。本イベントでは、南伊豆町の人のあたたかさや豊かな自然といった魅力は勿論、人口減やそれに伴った産業の衰退といった課題にも触れることができます。これまで南伊豆町と接点がなかった首都圏の大学生にとっては、本イベントが町との初めての出会いとなり、町や町民のみなさんとのご縁が広がる第一歩となるでしょう。こうした取り組みは、高い高齢化率や著しい人口減少という課題に直面している南伊豆町にとって、将来にわたり町を支える「関係人口」、いわば「住まずとも町の一員」の増加に直結することが期待されています。現在はその実施に向け、南伊豆町役場企画課地方創生室と密に連携し、準備を進めています。
施策名称:つながる田舎留学
主催:南伊豆町役場、田舎留学プロジェクト事務局
参加対象者・人数:首都圏の大学に在学する学生、30名
時期・期間:2025年9月18~24日(6泊7日)
参加者(学生)に生じる費用:本留学参加者の居住地〜南伊豆町までの交通費を除き、約13,000円程度(クラウドファンディングの結果に応じて、変更がある予定です)、宿泊費などについては町の予算より補助をいただきます。
滞在先:らいずや
活動内容:南伊豆町のみなさん(農家さん、猟師さん、漁師さん、ダイビングショップ等観光事業者さん、のお手伝い、町内全小中学校における2コマの授業、トコリンピック in 伊浜におけるスタッフ活動、観光(石廊崎、弓ヶ浜など)、南伊豆町のみなさんとの交流会、留学前勉強会など…


\ 田舎留学中のアクティビティから一部をピックアップしてご紹介します /
・学校連携プロジェクト
南伊豆町内には大学や専門学校などの高等教育機関が無く、それらに進学する学生の多くは町を出ます。つまり町内には20歳前後の人が極めて少なく、子どもたちは彼らと交流する機会がありません。すると、進学や上京を遠い存在に感じてしまい、自らの可能性を閉ざすことになりかねません。学校連携プロジェクトでは、町内すべての小中学校のご協力を賜り、学校で授業を開催させていただけることになりました。授業の内容は運営局のメンバーみんなで話し合いながら、双方にとって有意義な時間になるように企画します。
・ボランティア
南伊豆町にはさまざまな産業があります。農業、漁業、狩猟といった第一次産業から観光業や飲食業などの第三次産業まで。さまざまな事業者様にご協力いただき、ローテーションで参加メンバーがボランティア活動を行います。作業を教えていただいたり、昼食をボランティア先の方々と一緒に食べたりする中で、個人的な関係性を構築することを目指します。
・仲間との共同生活
田舎留学中は同じく参加する学生みんなで町内の宿「らいずや」様で共同生活。みんなで協力して、ご飯作りや掃除、洗濯などを行います。南伊豆町や地方創生、二拠点生活、移住などに関心を持つ仲間ができることもこのプロジェクトの大事な点のひとつです。ここでできた仲間と共に、田舎留学期間後にあっても南伊豆町のファンとしてのコミュニティを継続していきます。加えて、事前のレクリエーションや勉強会などさまざまな前後の企画を設定し、南伊豆町の魅力も課題も包括的に知ること、参加メンバー間、町民のみなさんとの心理的安全性の形成に努めます。
更に、南伊豆町役場、町民、そして参加メンバーにとって三方良しとなり、かつより本プロジェクトに参加する学生が関係人口になりやすいプログラムを構築することを目指し、以上にご紹介した25年9月の「つながる田舎留学」に加え、26年2月の「ふかめる田舎留学」や同窓会の実施、各種イベントへの南伊豆町ブースの出店など、通年でさまざまな施策を実施することを計画しています。その詳細につきましては、後述する【 さらに良い施策とするためにアップデート 】をご確認ください。
【 資金が必要な理由 】もっともっと多く、かつ関係性の濃い関係人口をつくるために
町の事業化が決定し、主として南伊豆町の予算を使用しながら実施する予定でした。しかし、そもそも本来の目的に立ち返ると、南伊豆町の未来をつくる関係人口を確保するための施策が町の財政を圧迫することは私たちの本意ではありません。
また、25年9月の「つながる田舎留学」以外にも、26年2月の「ふかめる田舎留学」など関係人口の醸成とプロジェクトの持続可能性を高めるためにさまざまな施策を実施を検討しています(詳細は以下に記載の【 さらに良い施策とするためにアップデート 】をご覧ください)。待ったなしの人口減、少子化、高齢化が進んでいくことに町のみなさんは大きな危機感を持っており、中途半端ではなく、インパクトのある絶大な効果を生むことが私たちに求められていることを感じ、より大きな効果を狙って事業推進を行います。しかし、そのためには更に多くの資金が必要になることが判明しました。
以上二点のため、町役場からのご支援だけではなく、南伊豆町や静岡県を愛するみなさん、地方創生や過疎化問題などにご関心があるみなさんに是非ともご協力をいただき、必ずやこのプロジェクトの関係人口創出効果の最大化と将来的な町の担い手の確保を実現したいと考えています。ご支援をよろしくお願いいたします。
【 具体的な使徒 】さまざなかたちで役立てられます
① 本留学中に使用する備品等の購入にかかる費用
例えば … 長靴、作業着、道具など、ボランティア先における作業に必要な備品(約¥80,000を想定)
② 広報活動、運営局員やライトメンバーの募集にかかる費用
例えば … ビラや資料の印刷、会議室のレンタル、備品等の南伊豆町からの輸送、広告(約¥100,000を想定)
③ 班ごとの準備活動やレクリエーションにかかる費用
例えば … 南伊豆町でのフィールドワークにおける交通費(町からの補助が無い場合)、ZOOM有料プラン(約¥100,000を想定)
④ プロジェクト実施後の活動にかかる費用
例えば … 稲門祭への南伊豆町ブースの出店、同窓会の実施、「卒業文集」の発行(約¥200,000を想定)
⑤ 春季「ふかめる田舎留学」にかかる費用
例えば … 南伊豆町でのフィールドワークにおける交通費(町からの補助が無い場合)(約¥100,000を想定)
⑥ CAMPFIREに支払う手数料総支援額の17%(内訳:掲載手数料12%+決済手数料5%)(別途消費税)
目標金額:¥678,600
*目標金額を越えた金額が集まりました場合、プロジェクトの運営にかかる費用に充てさせていただきます。ご支援いただきました金額をもとに、運営局内各班に配分し、各班の主体性と責任のもとで大切に使わせていただきます。
*上述の使徒に加え、お選びいただきましたリターンの仕入れ費用が発生します。リターンにより仕入れの費用は異なりますので、現状は上述に加えておりません。
【 さらに良い施策とするためにアップデート 】南伊豆町役場、町民、そして参加メンバーにとって三方良しとなるプログラムを
南伊豆町の関係人口の増加とプロジェクトの持続可能性を高めるため、23年度早稲田大学地域連携ワークショップ(南伊豆町)最終報告会以降に検討、考案した施策をご紹介します。24年度早稲田大学地域連携ワークショップ(南伊豆町)最終報告会にて提案させていただきました。これにより、「つながる田舎留学」を依然として中心に据えつつ、年間を通じた活動を展開し、南伊豆町役場、町民、そして参加メンバーにとって三方良しとなり、かつより本プロジェクトに参加する学生が関係人口になりやすいプログラムを構築することを目指します。
① みなみの桜と菜の花まつりにおける主体的なボランティア活動を通した「ふかめる田舎留学」の実施 〜夏季「つながる田舎留学」から春季「ふかめる田舎留学」へ〜
A. 町長のご提案により「みなみの桜と菜の花まつり」における主体的なボランティア活動を主とする「ふかめる田舎留学」を26年2月に実施することになりましたB. 従来から予定されている25年9月の田舎留学を「つながる田舎留学」と位置づけ、まずは南伊豆町と学生の縁を形成します。ここで南伊豆町のあたたかさに触れ「もっと関わりたい」「貢献したい」という意欲を持った学生には「ふかめる田舎留学」に参加してもらい、より濃い関係人口の形成を目指します
② 町役場の負担感の軽減
A. まちの関係人口の増加、ひいては町の将来を創ることを目的としたプロジェクトが町の財政を逼迫させることは本意ではありません。クラウドファンディングサイトを設立し、南伊豆町民のみなさまをはじめ、私たちのプロジェクトを応援して下さるみなさま、南伊豆町を愛するみなさまのお力添えを賜り、資金面において町から一定程度独立し、町の予算を軽減します。
B. 早稲田大学登録サークル化を行い、早稲田大学の持つファシリティ(会議室の使用など)を利用し、予算の削減を図ります。
C. 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター支援サークル化を行い、3万円のご支援を同センターからいただく予定です。
D. 運営局のフィールドワークは「ふるさとワーキングホリデー」制度を利用し、午前中は各事業者における就労、午後は田舎留学プロジェクト関連業務を行い、準備段階にあっても町に貢献できるよう努めます。
③ 東京を拠点とした「南伊豆町ファン」作り
A. 稲門祭2025への南伊豆町関連ブースの出店
B. 南伊豆町のファンコミュニティを形成、田舎留学後もファンとして南伊豆町に関わりやすい体制を構築します。南伊豆町におけるふるさとワーホリ、おてつたび、その他イベントの際に田舎留学参加者をお誘いしやすいような連絡ネットワークをつくります。
C. 卒業後に関係人口としても関わり続けるためのサポートを行います。「下賀茂田舎暮らし体験住宅」や「南伊豆るプロジェクト」などの情報を提供し、移住や二拠点移住のための具体的な方法を知る機会を提供します。
D. 町外における南伊豆町関連イベント(移住関連セミナー、姉妹都市などでのイベントなど)への出席、必要に応じてボランティア活動を行います。
④ 学生団体びよーんどとのアドバイザリーサポート協定の締結を通し、町内小中学生にもたらす教育的効果の最大化
A. 学生団体びよーんど(2023年設立、早稲田大学登録サークル、WAVOC支援サークル)と「アドバイザリーサポート協定」を締結し、協力関係を構築します。
B. 学校連携プロジェクトの内容決定のためのワークショップを学生団体びよーんどにおける会内勉強会として開催します。
C.学校連携プロジェクトの効果検証(生徒に対するアンケート調査など)を行い、報告書にまとめ、町に提出、及び個人情報を保護したうえで公表します。
D. びよーんどのメンバーに優先的に田舎留学に参加していただき、学校連携プロジェクトの補助をしていただく予定です。
*すべての実施が決定しているわけではなく、あくまで検討中のものです。クラウドファンディングの結果等に応じて、変更が生じます。
【 現在の準備状況 】頭がねじれるまで町の未来を考えています
2024.1-3 2023年度早稲田大学地域連携ワークショップが開催されました。ワークショップ内、最終報告会にて「田舎留学」の実施を町に提案させていただきました。

2024.10 町から「田舎留学」を提案した「まめたいチーム」5名に対して、町長より委嘱を受けました。正式名称を「田舎留学プロジェクト」としたほか、「南伊豆町長特命プロジェクト」として町と共に事業推進を行うことを確認しました。

2024.10 10月全体フィールドワークを実施しました。委嘱状の受領式、企画課地方創生室さんとの打ち合わせ、町長をはじめ町のみなさんとの懇親会などを実施しました。

*10月FWの様子はこちらから
https://note.com/inakaryuugaku/n/n0226b529b50f
https://note.com/inakaryuugaku/n/nb5564d0f0813
2024.12 12月全体フィールドワークを実施しました。留学中ボランティア先として参加メンバーを受け入れていただく事業者さんへご挨拶、プロジェクトのご説明を行いました。

*12月FWの様子はこちらから
https://note.com/inakaryuugaku/n/n4713cb68ccd7
https://note.com/inakaryuugaku/n/n5a5d256167e3
https://note.com/inakaryuugaku/n/n3eb44ce8e4e4
https://note.com/inakaryuugaku/n/n2df2193637b5
2025.1 2024年度早稲田大学地域連携ワークショップの開始に伴い、南伊豆町役場企画課地方創生室のみなさんが早稲田大学へ来学されました。メンバーが南伊豆町側として、ワークショップオリエンテーションに出席しました。

2025.1 一部のメンバーが訪町しました。プロジェクトの今後について、岡部町長や企画課地方創生室さんとの意見交換をしたほか、石廊崎オーシャンパークの皆様へご挨拶へ伺いました。

*1月FWの様子はこちらからhttps://note.com/inakaryuugaku/n/n48c57ae7aff4
ほか、仕事内容を事務局長、事務局長補助(経理)、宿班、ボランティア班、プロジェクト班、人事班、広報班と振り分け、各班ごとに随時活動を行っています。早稲田大学を拠点にミーティングを行うほか、必要に応じて各班が独自に訪町しています。関係機関さんや町内事業者さん、町役場さんと調整を行い、田舎留学プロジェクトの成功へ向けて活動しています。
【 今後のスケジュール 】春から新歓、新たなメンバーが加わります
2025.3 3月フィールドワークを実施します。町内事業者に対してスポンサー契約を打診、2024年度早稲田大学地域連携ワークショップ最終報告会における前年度経過報告、宿泊事業者と留学中の宿泊に関する打ち合わせ、田舎留学中に町内での実施が予定されている諸イベントとの関わり方に関する打ち合わせなどを行います。
2025.4 新歓期間とし、私たちとともにプロジェクトの運営を担う「運営局」メンバーとプロジェクトに参加し、南伊豆町の関係人口になる第一歩を踏み出す「ライトメンバー」を募集。南伊豆町マスコットキャラクター「いろう男爵」が来学を予定しています。
2025.5 運営局メンバー募集 締め切り(10名程度、田舎留学プロジェクトの運営を担うメンバーの加入を想定しています。加入後、班に振り分け、縦割りの中で活動していただきます)
2025.6 ライトメンバー募集 締め切り(15名程度、つながる田舎留学に参加してくれるメンバーの加入を想定しています)
事務局、及び運営局メンバーは役割分担し、早稲田大学を拠点とした準備活動、必要に応じて南伊豆町におけるフィールドワークを行います
2025.9.18-24 つながる田舎留学
【 リターンについて 】お礼をご用意しています
みなさまのご支援に対し、リターンをご用意しております。個人、法人を問わずご支援いただくことが可能です。みなさまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。
注意:本クラウドファンディングを通したご支援は、あくまで任意団体「田舎留学プロジェクト 運営局」に対するものであって、南伊豆町役場、早稲田大学、田舎留学プロジェクト事務局などは一切関係ございません。本クラウドファンディングによるご支援に対し、税制控除はありません。使途につきましては、任意団体「田舎留学プロジェクト 運営局」内での話し合いのもと、本施策の成功のために使用されます。なお、名称にはあらかじめご留意ください。
【 最後に 】日本の地方創生の在り方を問う、ファーストペンギンとして
ここまでお読みいただいてありがとうございました。私たちは、国が今後の地方の担い手として期待している関係人口の増加こそ、人口減少や高齢化といった南伊豆町の厳しい現状にもかかわらず、町に活力をもたらす大きな可能性を秘めていると考えています。私たちは町の自然や食の魅力、東京からのアクセス、来訪者に対する町の受容性の高さなどを鑑み、その最適解として「田舎留学プロジェクト」を考案し、岡部町長をはじめ多くの町の方々と共にその成功に向けて取り組んでおります。検討を進めていく中で、効果最大化のため、本プロジェクトに付随してより関係人口になりやすくする追加施策の実施、いわばアップデートを目指すことを決定し、今後は通年での活動を予定しております。これは日本各地を見渡しても類を見ない、行政、民間、住民、大学機関が連携し、学生の熱意と主体性の中で町の委嘱のもと行う前代未聞のプロジェクトであり、日本の地方創生の起爆剤になり得ます。しかしながら、そのためには町のみなさまのご理解、ご協力、そして金銭的なご支援が必要です。私たちの「第二の故郷」である南伊豆町の未来を創るという熱い決意をご信頼いただき、町の明るい未来に向けてみなさまと共に取り組んで参りたいと考えております。あたたかいご支援のほど、よろしくお願いいたします。
最新の活動報告
もっと見る
【 メンバーの想い 】「つながり」を起点に
2025/05/13 10:48田舎留学プロジェクト事務局でボランティア班・広報班リーダーを務めております、早稲田大学人間科学部 3年の河本結生です。はじめに、3月から続けてきたクラウドファンディングについて。今回の目標金額は698,800円。未達成の場合は全額が返金されるAll-or-Nothing方式という、まさに背水の陣とも言える状況の中、皆さまには長きにわたりご支援・ご協力をお願いしてまいりました。その結果、多くの方々から温かいご支援や情報拡散など力強い後押しをいただき、先日、無事に目標金額を達成することができました。本当にありがとうございます。5月10日に南伊豆町を訪れた際にも、町内各所に田舎留学プロジェクトのパンフレットやクラウドファンディングのチラシを掲示していただいている様子を目にし、改めて町の皆さまのご協力あってこその活動であることを実感いたしました。また、もともと南伊豆とご縁のなかった方々からも応援の声をいただく機会が増えています。本プロジェクトが少しずつ広がりを見せていることを大変嬉しく思うと同時に、改めて皆様に深く御礼申し上げます。ここで少し、田舎留学プロジェクト事務局の紹介をさせていただければと思います。田舎留学プロジェクト事務局は、事務局長を務める三井、人事班リーダーを務める山下、宿班・プロジェクト班リーダーを務める中村、そしてボランティア班と広報班のリーダーを務める私河本の計4名で構成されています。大学のワークショップで知り合った2023年12月から今日に至るまで、4人で全力で活動してまいりました。私がリーダーを務めるボランティア班と広報班についてもご説明を。ボランティア班では、9月に実施を予定している「つながる田舎留学」に向けて、参加学生がお手伝いをさせていただく町内事業者の皆さまとの調整を進めています。町のみなさんとの密な関わりを重視している本活動において、町と参加学生とを繋ぐ役割を担っています。広報班では、さまざまな広報媒体を通じて、情報発信を行っています。具体的には、南伊豆町回覧板(毎月1日・15日)や広報みなみいず(隔月)をはじめ、SNS(Instagram・X・Facebook・note・公式ホームページ)でも定期的に発信しています。ぜひご覧いただけますと幸いです。最近では、こうした媒体を通じて私たちの活動を知ってくださる方も増えているようで、町内外を問わず認知度が高まっていることを大変嬉しく感じています。大学では、4月より環境デザイン学ゼミに所属しています。建築や都市を対象としたフィールドサーベイを通じて、人間と環境の相互関係を明らかにすることを目指し、佐藤将之教授のもとで学んでいます。4月には、ゼミ活動の一環として兵庫県上郡町を訪問しました。同町は、佐藤教授が梅田修作町長の指導教員であったご縁から、早稲田大学人間科学学術院とまちづくり・教育分野で連携協定を締結しています。今回は町内各所への本棚設置に向けた現地調査を実施しました。町の中に本棚を設置することで、本を介して人と人とがつながる機会を生み出し、地域内での交流の促進を図ることが目的です。今後は今回のフィールドワークをもとに、設置場所や本棚のデザイン、交流を生みやすくする仕掛けなどを検討し、夏頃の設置を目指して準備を進めていきます。田舎留学プロジェクト、そして上郡町での活動のいずれにも共通しているのは、人と人とのつながりを大切にしている点。私自身、ボランティアや地域活動の経験は決して多くはありませんでしたが、南伊豆への思いを原動力に、活動をしてまいりました。これまで田舎留学プロジェクトを共に形にしてきた事務局メンバー、そして近々加わってくれるであろう新たな仲間たちとともに、今後もより一層、人と人、そして地域と人をつなぐ活動に励んでまいります。最後になりますが、これからの私たちの活動においても、変わらぬご支援、ご声援をいただけますと幸いです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 もっと見る
【 メンバーの想い 】 「人のあたたかさ」を大事にした施策に
2025/05/12 17:20初めまして!田舎留学プロジェクト事務局で宿班・プロジェクト班リーダーを務めております、早稲田大学政治経済学部3年の中村友泉です。クラウドファンディング終了まで残すところあと3日。皆様のおかげで目標金額を達成することができました!多大なるご支援ありがとうございます。まずは自己紹介から。大学では経済を専攻しており、今年度よりPOSデータ(販売情報)の分析を行うゼミに所属しています。データ分析といった、理論だけではない実践的な学びというものを自分の主軸としています。学問分野は地方創生と離れたものですが、高校生の頃から漠然と興味を持っており、大学主催の「地域連携ワークショップ」への参加を機に本プロジェクト事務局として活動しています。これまで地方や海外におけるボランティアや研修などの経験がないため、当初は不安な気持ちも大きかったですが、試行錯誤しながら、プロジェクト実施に向けて準備を進めています。もともと南伊豆町については名前も知りませんでしたが、フィールドワークを繰り返す中で気づいた、弓ヶ浜や石廊崎などの自然、桜や菜の花、海産物やいちごをはじめとする名産品といったポテンシャルの高さにはびっくり。そして何よりも魅力に感じたのが「人のあたたかさ」。首都圏で育ってきた私にとって、親戚のように皆さんが気軽に挨拶してくださる南伊豆町は「第二の故郷」のような存在です。さて、私は田舎留学プロジェクト事務局において、宿班とプロジェクト班のリーダーを務めております。ここで活動報告の代わりに、私が担当する二つの班の進捗状況や今後の指針についてお話しさせていただきます。まずは宿班から。すでに知ってくださっている方も多いかと思いますが改めて、本プロジェクトの最も主たるイベント「つながる田舎留学」では、2025年9月18日から24日の1週間、首都圏の大学生30名が南伊豆町に滞在し、様々なアクティビティを行います。「つながる田舎留学」の主軸となっているのは「住まずとも町の一員になる(=関係人口)」擬似体験をすること。そこで、本イベント中は、従来の受動的な観光とは異なり、全員が協力して自炊や掃除を行う共同生活をします。その手配や管理を行うのが宿班です。今回宿泊させていただくのは、弓ヶ浜から徒歩圏内にある「らいずや」様!調理スペースやBBQ場、ミーティングや交流の場として利用できるフリースペースなども揃ったとてもきれいな宿です。現在は、らいずや様との打ち合わせを重ね、共同生活の詳細な部分を詰めているところです。また、本イベント中は参加者全員が日替わりで自炊をすることを考えています。今後は、運営局のメンバーを迎え、宿泊のみならず食事やボランティア先への送迎などについても検討していきます。次にプロジェクト班。こちらは、町内の小中学校で授業を開催する「学校連携プロジェクト」の企画立案および運営を行う班です。南伊豆町内には大学や専門学校などの高等教育機関がなく、子どもたちが20歳前後の学生らと交流する機会がほとんどないというのが現状。そこで、普段は関わる機会のない首都圏の大学生と南伊豆町の児童・生徒が交流することで、互いが新たな価値観や生き方に触れ、理解を深めることができると考えています。12月FWの際には、町内学校を訪問し、校長先生・教頭先生方にご挨拶をさせていただきました。また、4月には本プロジェクトの効果最大化のため、東京都内の公立中学校で学習支援を行う「学生団体びよーんど」様とアドバイザリーサポート協定を締結いたしました。地方創生と教育の知見を組み合わせ、大学生と町内の児童・生徒の双方にとって有意義な企画を作れるよう、精進してまいります。もともとは「つながる田舎留学」のみの提案から始まった田舎留学プロジェクト。参加者が継続的に南伊豆町と関わっていく仕組みを作っていくためにどんどんプロジェクトの内容を膨らませていますが、その中でも「人のあたたかさ」「人とのつながり」という部分が根幹であり続けることが大事だと思っています。東京での作業が机上の空論にならないように、できるだけ南伊豆町を訪れる機会を増やし、準備を進めていきたいと思います。これからも、町の皆さんとの関わりを大切にしながら、精力的に活動していきます。最後に、田舎留学プロジェクトのクラウドファンディングが残すところ3日となりました。ありがたいことに当初の目標金額を達成いたしましたが、ネクストゴールを設定し、最後までご支援を受け付けております。南伊豆町の魅力を肌で感じ、「住まずとも町の一員になる」若者を増やすために、引き続きご支援のご協力をよろしくお願いします。 もっと見る
【 メンバーの想い 】人と出会い、まちとつながる
2025/05/12 15:43こんにちは。田舎留学プロジェクトで事務局人事班リーダーを務めております、早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科4年の山下こころです。私は現在、都市における人の流れ(人流)をモデル化し、建物や駅の配置を最適化する研究に取り組んでいます。これは、都市の利便性や安全性を高めるために欠かせない分野で、4月に研究室に配属されてから日々試行錯誤を重ねながら学びを深めています。まちづくりに関心をもつようになった原点は、高校1年生のときに訪れたフィリピンでの体験でした。スラム街と高層ビルが隣り合って存在する光景に衝撃を受けると同時に、どちらに住む人々も同じような笑顔を見せていたことがとても印象に残りました。この経験から「すべての人が安心して暮らせる社会をつくりたい」と考えるようになり、街づくりを通じて社会に貢献できる道を選びました。その想いを胸に、大学ではボランティアサークルに所属し、岩手・徳島・新潟など全国各地の地域を訪れてきました。地域の方々と継続的に関係を築きながら、それぞれの土地の魅力や課題を学ぶ機会を得ています。そうした中で、サークル外でもっと深く地域と関わる場を求めていたときに出会ったのが、早稲田大学GCCオフィスが主催する地域連携ワークショップ。そして、そこから生まれたのが今の「田舎留学プロジェクト」です。研究の面でも、地域課題と都市設計はつながっています。たとえば、フィリピンで深刻な交通渋滞が経済活動にまで影響を及ぼしていると知った経験から、「都市構造をもっと良くしたい」という思いが芽生えました。今の研究テーマは、そんな原体験と問題意識から選んだものです。私は大学院には進学せず、卒業後は就職を予定しているため、残された1年という時間を最大限活かして、自分の関心をとことん深めていきたいと考えています。田舎留学プロジェクトに関われるのも、残り1年。ですが、卒業後も南伊豆には定期的に通い続けたいと思っています。東京から車で約4時間。週末に友人を連れて訪れる日を今から楽しみにしています。現在は、人事班のリーダーとして、プロジェクトに共感し、一緒に南伊豆と関わってくれる仲間を募っています。立ち上がったばかりのこのプロジェクトですが、丁寧に説明を重ねることで、関心をもってくれる学生も少しずつ増えてきました。「南伊豆に継続的に関わりたい」と思ってくれる仲間を、これからも増やしていきたいです。そして最後に。私たちの活動に賛同し、クラウドファンディングという形で応援してくださる方を募集しています。学生たちがそれぞれの経験と想いを結集し、本気で南伊豆と向き合っています。どうか温かいご支援をよろしくお願いいたします。 もっと見る










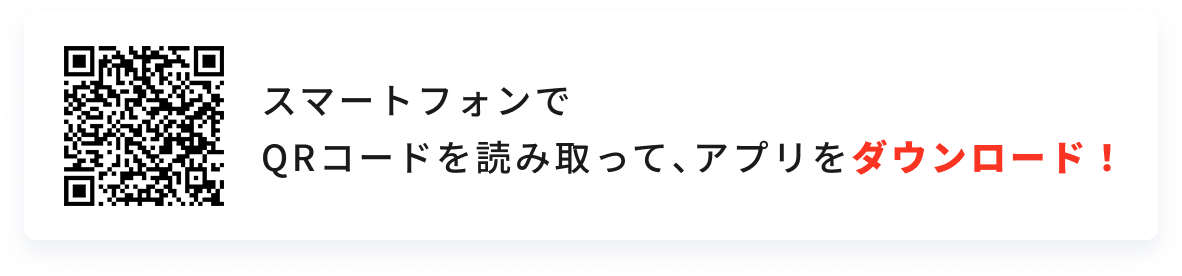


コメント
もっと見る